
カトリック(キリスト教)の精神に基づいて、子どもの発達を助長する
「神さまが喜ぶことは良いこと」「神さまが悲しむことは悪いこと」というカトリック(キリスト教)の明確な価値観を身につけ、神さまが喜ぶことを実践できる人(光の子)を育てる

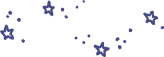
カトリック(キリスト教)の精神に基づき、
子どもたち一人ひとりの無限の可能性を信じ、
子どもたちの人間的基礎(生きる力の基礎)を育む
カトリック(キリスト教)の精神に基づき、
子どもたちの発達を助長する
(純粋で感性豊かな幼児期に神さまとの
出会いを援助し、神さま・自然・友達
との出会いを大切にする)
カトリック(キリスト教)の明確な価値観を身につけた子どもたちが、神さまが喜ぶことを実践できる正義の光で世の中(変化の激しい21世紀)を照らす人(光の子)になる


「神さまが喜ぶことは良いこと」「神さまが悲しむことは悪いこと」というカトリック(キリスト教)の明確な価値観を身につけ、神さまが喜ぶことを実践できる人(光の子)を育てる

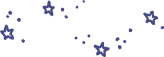

幼稚園は小学校以降の教育を先取りして教え込む予備校ではなく、子どもが主体的に人生を歩むための基礎をつくる幼児教育機関である。子どもが「やりたいこと」を十分に学び込める環境や自発的に活動できる環境を準備し、幼児期にしか出来ない経験や体験が出来るようにすることが重要であり、幼児期を幼児として伸び伸び過ごすことが子どもの心と体を健やかに成長させる。充実した幼児期を過ごせた子どもは人間的基礎(生きる力の基礎)を育み、児童期には学び込める子どもになっていく



結果や成果ではなく、取り組みのプロセスを重視する教育及び保育。ワークブックによる読み書きや計算といった知育教育ではなく、子どもがやりたいと思う遊びを夢中で集中して遊び込むことで、主体性や意欲や頑張る力、協調性、共感力、思いやり、社交性、自律性などの非認知能力が養われる。心の力である非認知能力は未来につながる力“社会情動的スキル”(目標を達成する力・他者と協力する力・情動の抑制など)ともいわれている。人生を心豊かに幸せに生きていくことができるといわれているこの力(人生の土台となる力)を身につける教育および保育、これが
21世紀型の幼児教育である


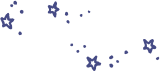
神さまから愛されていることを心地よく感じ取り、安心感と自信を持ち、行動規範の源が「神さまを喜ばせたい」から始められる人となることで、心豊かな人生を送れるようになってほしい
自然と出会い、自然に親しみ、五感を通し、驚きや感動と共に、命の尊さ・感謝の気持ち・優しさ・好奇心・探求心など、豊かな心を育みたい
一人では出来ないこともみんなで力を合わせれば実りとなる。敬愛し合える関係を心地よく味わいながら、相手を思いやるようになってほしい
わたしたちはみんな分け隔てなく神さまから愛(大切に)されています。例え神さまなんて信じないと言ったとしても、神さまはわたしたちみんなを大切にしてくださっているのです。そんな神様の気持ちに気づいて欲しいのです。そして一緒にありがとうと感謝の祈りを捧げたいのです。神さまの気持ちに気づくと、この世界が本当に恵みに満ちていることがわかるはずです。それに気づいたらきっと神さまに感謝したくなるはずです。そして、自分だけが愛されているのではなく、周りにいるみんなが同じように大切にされていることに気づいたら、神さまから大切にされている者同士、お互いを大切にし合えるはずだと気づくはずです。自己中心や利己的な考えから抜け出して、神さまを大切にし自分を大切にするのと同じように、周りのみんなを大切にしようという考え方(隣人愛)が、すなわちカトリックの精神なのです。認定こども園マリア幼稚園ではイエス・キリストの教えとその生涯を手本にしながら、神さまへの感謝と神さまとの出会いという宗教的環境に、純粋な感受性をもった幼児期に接する事は、人として生きていく上でとても大きな大切なお恵みとなると考えているのです。本当の意味での豊かな心や良心が育まれて行くと考えているのです。
子ども達が、先生の指示や大人の指示を求めて行動するのではなく、自らの興味や関心によって、自主的自発的に活動し生き生きと行動している姿を伸び伸びと言います。「先生、次なにするんですか?」と、6才を前にして、すでに指示を待つ子どもなどにはなって欲しくないと思っていますし、そのような子ども達のことを決して伸び伸びしているとは言いたくはありません。認定こども園マリア幼稚園は、子ども達の成長や発達に見通しを持ち、明確な意図をもった幼児教育を展開しているとの自負があります。簡単に「あっちに行っちゃダメ」「それを使っちゃダメ」なんでも「ダメ」という環境ではなく、「いっていいよ」「やっていいよ」「どうぞどうぞ」という、園と保育者の「いいよ」の姿勢によって、子ども達は常に肯定的にその活動や行動を見守ってもらえると共に、発達段階にあった取り組みでの応援や励ましそして信じて持ってもらえる環境と関係性があるからこそ、当然のこととして伸び伸びとした姿が見られるのです。勿論、伸び伸びは決して野放しではありません。園生活の中で積み重ねられていく秩序ある取り組みと日常的な協働的な活動を通して、自己発揮だけではなく、感謝や自己抑制も当然の事として身につけ、正しいことを自分で考え自分で判断し自分で行動する力が身につくよう援助しています。ですから伸び伸びと言えるのです。
未完成な大人とは、大人を基準にして、大人の出来ることを同じようにするのが当たり前と捉える考え方です。その場合幼児や児童のする事への評価は、「子どもは大人に比べて何もできない。これもできない、あれもできない、ダメな子だ」になります。子どもですから、大人と同じように出来ないのが当たり前なのですが、常に早くしなさいとせかされ、否定的に評価されてしまう捉え方です。それに比べて未成熟な人間と捉えることは、その時々の発達の特性や発達段階を考慮し、成長する見通しをもって信じて待ち援助する捉え方ですから、「これもできるようになった、あれもできるようになった、いいねすごいね」と、一つ一つの成長発達を一緒に喜び合えるのです。かけがえのない大切な幼児期の子ども達を、どのように考え捉えるかによって、子ども達への指導援助は根本的に異なってきますね。
文字や数に関する学習に代表される、五十音のように記号化されたものだったり、単純な数字で構成される認知能力に力を入れた教育は、確かに知的好奇心として幼児にとっては甘い甘い蜜のようなもので、一度その情報の量と伝達のスピードに接すると、虜になってしまうものなのです。そして困ったことにそれらは成果が出やすく見た目に評価がしやすい認知的能力なので、周囲の大人たちまでも巻き込んでその虜になってしまいがちなのです。 しかし、実は大きな落とし穴がそこにはあるのです。そのような学習は早く学んだほうがいいとは限らないものなのです。次の児童期を前にした幼児期は、日常的な生活の中での実際の体験や経験と言った、自分でやってみた活動によって、自分がこれから歩む人生の、最も根本的な概念や自分なりの価値観や情緒を培うのに必要不可欠な時期なのです。この時期をどれほど丁寧にそして豊かに過ごせるかによって、その後の人生が大きく豊かな広がりをもって行くかが、左右されてしまう時期なのです。逆に言えば、小学校で習える文字や数などの認知能力に時間をとっている暇はないのです。感受性の強い純粋な好奇心にあふれた幼児期に、園生活の限られた貴重な時間の中で、神さまに出会い、自然に親しみ、友達と協力し合って、直接本物を見たり触ったり感じたりすることが、人としての大きさを増す土台作りには欠かせない事なのです。認定こども園マリア幼稚園は、子どもたちが絵本を見たとき、その綺麗な絵を見て先ず「きれい!」と言って欲しいのです。絵本を見てその絵ではなく「ちょうちょ」や「とんぼ」とかかれた文字をとんとんと読んで「どう、わたし字が読めるのよ、すごいでしょ」と言うような子どもにはなって欲しくないのです。誤解のないようにつけくわえておきますが、「自分のなまえがわかり(読める)、1から10程度までは数えられる」を一応の目安として、主に視聴覚的に日常生活の中で文字や数に関する概念には接してはいますから、当たり前のことですが、全く知らないとか絶対に接しさせないという事はありません。
恵まれた環境を十分に活かし、人間関係を大切にしながら、伸び伸びと園生活を送れるよう保育課程を設け、常に一人ひとりの成長発達に即した指導援助を実践しています。
静的な活動と動的な活動をバランス良く配置し、落ち着きや集中、活発さや忍耐等の育成に配慮しています。
成長発達への明確な見通しを持ち、それぞれの個人差、成長や発達の過程を理解し、幼児一人ひとりが直面する発達課題を、丁寧に見守り、共通理解を基に適切な指導援助を実践しています。
クラスは年齢ごとの横割りで設定していますが、子ども達が自主的自発的な遊びを展開する時間などには、異年齢児とも関わり相互に刺激し合えるように、縦割り的にも遊んだり活動したりできるようにしています。
活動に応じた机や椅子の出し方、発達段階に応じた保育室の環境設定、季節や時期ごとに配慮された園庭遊具やその配置等々、常に教育的な意図をもった様々な環境の構成に力を入れ、子ども達が自分たちで環境に関わり学び込める環境作りに力を入れています。
園生活全般において、一斉やグループでの指導、個別の指導、異年齢児と合同の指導等、様々な形態の指導援助を常に工夫検討し、より有効な指導援助を実践しています。
パソコンやドリルなどを使って文字や数を教科のように教える保育は行っていません。運動、文字の認識や数値的な理解の基礎、言葉や音楽的素養、様々な表現活動等は、日常的な園生活の中でバランスよく、自然なかたちで経験できるようにしています。
色紙や様々な制作素材は、園児一人一人が自分なりの制作を楽しんだり、満足いくまで繰り返し作りこみ、想像性を高めると共に、達成感や充実感を味わえるよう、十分に検討準備し、使用できるようにしています。